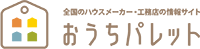こちらのページではスウェーデンハウスの坪単価に関する情報を掲載しています。
本記事は下記アンケートを基に作成しています。
・調査日:2022年10月24日~2022年10月31日
・集計対象:事前調査で「大手ハウスメーカーで注文住宅を建てたことがある」と回答した20歳以上の男女
・調査人数:事前調査12016人/本調査29人
・調査機関:サーベロイド(株式会社マーケティングアプリケーションズ)
・調査依頼:おうちパレット
スウェーデンハウスの調査アンケート詳細はこちら
スウェーデンハウスを検討する前に知っておくべきこと
【PRタウンライフ】
注文住宅を建てる際に一番重要なことは、注文住宅会社選びです。
選んだ注文住宅会社によって、建てられる家のデザイン、性能、価格が大きく異なります。
例えば注文住宅会社選びの失敗例としては以下のようなものがあります。
・A社でマイホームを建てたが、B社で建てればもっと安くて性能もデザインも良い家を建てられることが後から知った。せっかく建てたマイホームに自信と愛着が持てなくなってしまった。
・1社から間取りの提案を受けて、注文住宅会社のおすすめの通りに進めた結果、家が完成し実際に住んでみると間取りや収納が自分のライフスタイルと合わずに、気に入らないマイホームになってしまった。
注文住宅会社選びを失敗してしまうと、せっかくの人生を懸けて購入したマイホームが気に入らないものになってしまいます。そのため、注文住宅会社選びは絶対に失敗したくないポイントです。
注文住宅会社選びで失敗するリスクを減らすためには複数社から「カタログ」や「見積もり」、「間取り提案」を貰うと良いでしょう。
ただし、1社1社自分で気になる注文住宅会社に問い合わせすると、あまりにも手間がかかってしまいますので、一般的には資料一括請求サービスが利用されています。
中でもおすすめのサービスが「タウンライフ家づくり」と「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」です。
外装や内装のアバウトなイメージは「LIFULL HOME’S」を利用すれば、ある程度決められますが、実はマイホーム造りで失敗が多いのが家の間取り設計です。
後悔のないマイホームを建てるなら間取りの検討・精査は必須と言えます。
マイホームの間取りの検討をする際に、多くの方が利用されているのがこの「タウンライフ家づくり」です。
タウンライフ家づくりは各社から「あなたの希望に合わせたオリジナル間取りプラン」を貰うことができます。
注文住宅を建てるなら、こちらはやっておきたいです。
↓さらに詳しく知りたい方はこちら↓
一方で、マイホームを検討している方でまだ「何から始めればよいかわからない」という方は、まず複数社のカタログを見比べて、自分の希望のマイホーム像を具体化する作業から始めましょう。
LIFULL HOME’Sは、あなたの希望の条件に合った注文住宅会社のカタログを無料で一括請求できるサービスです。賃貸でもおなじみのHOME’Sを運営している、日本最大級の住宅情報サイトなので安心です。
あなたの地域に対応しているハウスメーカー複数社の住宅カタログを見比べたいばという方はLIFULL HOME’Sを活用してください。
↓さらに詳しく知りたい方はこちら↓
LIFULL HOME’Sもタウンライフも、資料請求の入力フォームは数分で完了できるので、両方とも行うべきでしょう。
今後何十年も付き合っていくマイホームのために、徹底的にリサーチして、計画を練り、後悔のない最高のマイホームを建ててくださいね!
- 1 スウェーデンハウスの坪単価は80万円~100万円程度
- 2 【おうちパレット独自調査】実際にスウェーデンハウスで建てた人の坪単価データ一覧
- 3 スウェーデンハウスの商品毎の坪単価
- 4 スウェーデンハウスの実際の建築事例から見る、3階建ての間取り
- 5 スウェーデンハウスのメーカーの特徴
- 6 スウェーデンハウスの家の性能
- 7 スウェーデンハウスを選ぶメリット
- 8 スウェーデンハウスのデメリット
- 9 会社情報
- 10 スウェーデンハウスの対応エリア
- 11 スウェーデンハウスの2024年4月のキャンペーン・イベント一覧
- 12 実際にスウェーデンハウスで家を建てた方の満足度評価と評判・口コミ
- 13 スウェーデンハウスの坪単価についてのよくある質問
- 14 ハウスメーカー選びを失敗しないためのポイント
- 15 坪単価についての基本情報
- 16 スウェーデンハウスのアンケート調査概要
スウェーデンハウスの坪単価は80万円~100万円程度
スウェーデンハウスの坪単価は80万円~100万円程度となっています。
スウェーデンからの輸入住宅ということもあり大手のハウスメーカーと比較しても坪単価が高く、一般の家庭ではなかなか手が出しにくい価格帯となっています。坪単価80万円程度の住まいを建てるとすると、日本で家を建てる平均的な坪数は約43坪といわれていますのでだいたい3500万円弱の費用になります。この費用にオプションや住宅ローン等が加わってきますので約3900万円の費用が必要になると考えておいた方が良いでしょう。
坪単価はなぜ高い
スウェーデンハウスの坪単価が高い理由はいくつかありますが、最大の理由はスウェーデンから輸入しているという点でしょう。断熱材やトリプルガラスの木製サッシをはじめ、水回りなどの設備にもオリジナルの設備が使用されています。それらの設備も輸入によって仕入れているので、その分のコストが坪単価を跳ね上げています。
しかし、ただ高いだけでなく、それだけの見返りもあります。計画換気システムや日本トップクラスの気密・断熱性能、100年住み継げるほどの耐久性など、コストに見合っただけのリターンをもたらしてくれます。実際にスウェーデンハウスは、実際に購入した人からも高い評価を受けており、一生に一度の大きな買い物で損をする可能性は低いでしょう。
また今日では、若い世代向けの高機能住宅なども手掛けており、リーズナブルな商品を取り扱っていくという動きもあるので、ぜひ注目したいハウスメーカです。
坪数ごとの本体価格と建築総額の目安
スウェーデンハウスで家を建てる場合の坪数ごとの本体価格を、上記で算出した坪単価を使って計算しました。これに付帯工事費や諸経費などで2割~3割程度プラスした金額が建築総額になります。あなたの建てたい家の広さと照らし合わせて、実際にかかる建築費用を検討してみてください。
| 坪数 | 本体価格 | 建築総額 |
| 25坪 | 2,000万円~2,500万円 | 2,667万円~3,333万円 |
| 30坪 | 2,400万円~3,000万円 | 3,200万円~4,000万円 |
| 35坪 | 2,800万円~3,500万円 | 3,733万円~4,667万円 |
| 40坪 | 3,200万円~4,000万円 | 4,267万円~5,333万円 |
| 45坪 | 3,600万円~4,500万円 | 4,800万円~6,000万円 |
| 50坪 | 4,000万円~5,000万円 | 5,333万円~6,667万円 |
大手ハウスメーカーとの坪単価比較
スウェーデンハウスの坪単価を大手ハウスメーカーと比べてみます。
| ハウスメーカー | 坪単価 |
| スウェーデンハウス | 80万~100万円 |
| 三井ホーム | 80万~130万円 |
| 積水ハウス | 50万~100万円 |
| パナホーム | 70万~150万円 |
| セキスイハイム | 59万~130万円 |
| ダイワハウス | 70万~150万円 |
| ミサワホーム | 60万~150万円 |
| ヘーベルハウス | 80万~120万円 |
| 住友不動産 | 50万~80万円 |
| 住友林業 | 60万~100万円 |
| タマホーム | 30万~80万円 |
| トヨタホーム | 70万~110万円 |
| 一条工務店 | 50万~90万円 |
| アキュラホーム(AQ Group) | 50万~80万円 |
| クレバリーホーム | 55万〜60万円 |
| アイフルホーム | 25万~65万円 |
| ユニバーサルホーム | 50.4万~92万円 |
大手の有名なハウスメーカーの坪単価は、一般的に平均70万円以上といわれています。スウェーデンハウスは坪単価平均80万円~100万円なので、大手ハウスメーカーと比べて高めの価格帯と言えます。予算よりもこだわりを重視したいという方は一度スウェーデンハウスを検討してみると良いでしょう。
【おうちパレット独自調査】実際にスウェーデンハウスで建てた人の坪単価データ一覧
スウェーデンハウスで実際に注文住宅を建てた方29人にアンケートを取った結果、実際の坪単価の平均は87.9万円/坪でした。
> スウェーデンハウスに関するおうちパレット独自調査データはこちら
坪数ごとの坪単価を見てみましょう。
30坪台で建築した家の坪単価データ一覧
| 坪数 | 建築価格 | 間取り/階数 | 工法 | 坪単価 |
| 30坪 | 3000万円 | 3LDK/2階建て | 木造軸組(在来工法) | 100万円/坪 |
| 32坪 | 3000万円 | 4LDK/2階建て | ツーバイシックス | 93.8万円/坪 |
| 32坪 | 3560万円 | 4LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 111.3万円/坪 |
| 34坪 | 3400万円 | 4LDK/2階建て | プレハブ工法 | 100万円/坪 |
| 34坪 | 2980万円 | 3LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 87.6万円/坪 |
40坪台で建築した家の坪単価データ一覧
| 坪数 | 建築価格 | 間取り/階数 | 工法 | 坪単価 |
| 40坪 | 3000万円 | 4DK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 75万円/坪 |
| 42坪 | 3950万円 | 4LDK/2階半 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 94万円/坪 |
| 41坪 | 3000万円 | 4LDK/2階建て | プレハブ工法 | 73.2万円/坪 |
| 48坪 | 3000万円 | 5LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 62.5万円/坪 |
| 48坪 | 4280万円 | 4LDK+Den/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 89.2万円/坪 |
50坪台で建築した家の坪単価データ一覧
| 坪数 | 建築価格 | 間取り/階数 | 工法 | 坪単価 |
| 52坪 | 3850万円 | 5LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 74万円/坪 |
| 50坪 | 3500万円 | 4LDK/2階建 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 70万円/坪 |
| 55坪 | 4500万円 | 4LDK/2階建 | 木造軸組(在来工法) | 81.8万円/坪 |
60坪以上で建築した家の坪単価データ一覧
| 坪数 | 建築価格 | 間取り/階数 | 工法 | 坪単価 |
| 60坪 | 3500万円 | 7LDK/2階建て | 木造軸組(在来工法) | 58.3万円/坪 |
| 89坪 | 6800万円 | 4LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 76.4万円/坪 |
| 75坪 | 4000万円 | 5LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 53.3万円/坪 |
| 70坪 | 4000万円 | 4LDK/2階建て | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) | 57.1万円/坪 |
坪単価でハウスメーカーを選ぶのは危険!?
注文住宅の検討方法として、坪単価でハウスメーカーを選ぶことはおすすめしません。安く建てた家は安いなりの理由があります。例えば、耐用年数が低く、20年~30年で建て替えが必要になり、建て替え費用として3,000万円かかってしまうケースが考えられます。
ハウスメーカー選びでは、失敗しないためのポイントをしっかり理解して、コスト以外に機能面などトータル的に比較した上で選ぶ必要があります。失敗しないためのポイントについては、下記にまとめていますので参考にしてみてください。

注文住宅を建てる際に依頼するハウスメーカーや工務店は全国で1000社以上存在します。その中には、いわゆる欠陥住宅を建ててしまう会社も存在します。多くの人にとって注文住宅は人生で1度きりの大きな買い物。『何千万円をかけて建てた夢のマイホームが欠陥住宅でした』では人生の取返しがつかなくなってしまうかもしれません。
そんなハウスメーカー選びで失敗しないために絶対におこなうべきことは、複数の注文住宅会社を比較検討することです。
複数会社を比較しないとこんなデメリットが…
他のハウスメーカーなら同水準でもっと安く建てられることを建てた後に知った…
建てた後に他の人の家を見て、もっとデザインを色々検討すべきだったと後悔…
1つの会社の話を鵜呑みにしてしまい、まともに条件・料金交渉ができなかった…
複数社から「間取りプラン」を貰っておけば、今まで想像していなかった、あなたにピッタリのデザインが見つかる可能性が増え、気に入った会社が見つかった際に料金面で適正かどうか自分で比較検討することも可能です。
人生最大級の買い物であるマイホームだからこそ、できるだけ失敗するリスクは減らして、後悔のないようにしたいですね。
複数会社を一括検討するなら「タウンライフ」か「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」を使うと良い
結論から言えば、一括資料請求サービスは「タウンライフ」か「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」を利用しておけば間違いありません。
両サービスとも、完全無料で利用できるので、あなたの用途に合わせて利用してみてくださいね!
両方利用される方も多いので、しっかり検討したい方は、両方登録しておきましょう。
自分の理想の家のイメージが決まっている方は「タウンライフ」で見積もりや間取りプランを貰い、具体化していこう!

タウンライフは、家づくりに必要な「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」を複数の住宅業者から一括請求できるサービスです。
サイト内で希望のエリアを入力し、計画書作成依頼することで、複数の会社があなたの希望に合わせた計画書を作成してくれます。
この間取りプランや見積もりなどを比較した上で、あなたの希望に合いそうな注文住宅会社を選ぶと良いでしょう。
タウンライフは全て無料で利用できるので、注文住宅を検討している方は一度使ってみるべきサービスです。
無料であなた専用の家づくり計画書を作ってくれる
たった3分でネット一括依頼ができる
厳選された優良注文住宅会社600社から相見積もりを取れる
↓さらに詳しく知りたい方はこちら↓
注文住宅を検討し始めの方は「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」でカタログ一括請求しよう!

LIFULL HOME’Sは注文住宅のカタログを一括で無料お取り寄せできる、資料一括請求サービスです。
注文住宅の検討を始めたばかりの方はこちらのカタログ一括請求サービスを利用すると良いです。
注文住宅の最初の一歩目は「どんな家を建てたいか、イメージを具体化すること」です。
LIFULL HOME’Sなら、あなたが検討している地域に対応しているハウスメーカーのカタログを一括請求できるので、そのカタログを見て、どんな家を建てたいかイメージを固めましょう。
一部上場企業「株式会社LIFULL」が運営している安心感
たった数分で、複数のハウスメーカーの一括カタログ請求依頼ができる(無料)
掲載のハウスメーカーはLIFULLが厳選した優良住宅メーカー
↓さらに詳しく知りたい方はこちら↓
スウェーデンハウスの商品毎の坪単価
スウェーデンハウスの人気商品毎の坪単価と特徴を紹介します。
mjuk(ミューク)の坪単価は80万円〜100万円程度

ミュークの坪単価は80万円〜100万円程度となっています。
ミュークはスウェーデン語で「やわらかい」という意味があり、「つよく、やさしく、やわらかく」と解釈することで、意志を持ってしなやかに生きる女性を象徴するキーワードにとらえた商品です。
ミュークには5つのポイントがあり、それぞれ自然に集まり家族がふれあう「ファミリールーム」。パブリックな性格を持ち、おもてなしを楽しむ「リビングルーム」。スウェーデン語で「お茶をする」という意味の、好きなものに素顔で向きあう場としての「フィーカ」。自然を身近に感じ、その恵みをいただく家庭菜園の「コロニーロット」。家族の思い出をめくる時間を大切にする「ライブラリー」。これらは、何気ない日常をとても楽しそうに話すスウェーデンの女性の在り方から学んで作られています。
Björk (ビヨルク)の坪単価は75万円~90万円程度

ビヨルクの坪単価は75万円~90万円程度となっています。
スウェーデンハウスが手掛けている、北欧デザインが魅力的な平屋住宅です。ビヨルクとはスウェーデン語で「白樺(しらかば)」を指し、木のぬくもりを五感で感じられるような心安らぐ住まい。平屋なので大地に近く、一歩外へ踏み出すとすぐに自然が広がっています。
ワンフロアでバリアフリー設計となっているゆったりとした平屋に、間仕切りの少ないゆるやかにつながった空間は家族との一体感を感じさせてくれます。スウェーデンハウスの特徴である高気密・高断熱はもちろん悠の住処にも取り入れられており、外気に触れる面積が多く、影響を受けやすい平屋でも1年中春のような心地よさを感じることが可能です。
SAKITATE(サキタテ)の坪単価は65万円~80万円程度

サキタテの坪単価は65万円~80万円程度となっています。
サキタテは、高級なスウェーデンハウスの商品の中でも比較的安めの価格設定で、20代の夫婦に向けた商品です。コストダウンしても、性能は他の商品そのままに快適な住まいとなっており、もちろんサポートシステムも変わりません。20代の夫婦向けとなってはいますが、高級なスウェーデンハウスの商品を比較的安く購入できることから他の世代にも人気となっています。
シンプルで広々とした間取りは可変性が高く、家族構成やライフスタイルに応じた自由自在の間仕切りが可能です。洗濯物は一般的に2階で干す家庭が多いですが、水まわりが2階にまとまっているので洗濯してから干してしまうまでスムーズな家事動線となっています。大量に食材をストックすることができる大きなパントリーや、玄関にはベビーカーなどもしまえるシューズクロークなど収納性も抜群な新生活を支える設計です。
HUS ECO ZERO(ヒュースエコゼロ)の坪単価は80万円~100万円程度

https://www.swedenhouse.co.jp/
ヒュースエコゼロの坪単価は80万円~100万円程度となっています。
ヒューズエコゼロは標準仕様のままZEHの性能をクリアしたエコハウスです。ZEHとはエネルギーの消費を最大限抑えつつ、自宅でエネルギーをつくることでエネルギー収支ゼロを目指した住宅のことで、国が推奨している未来の住宅です。スウェーデンハウスの住宅はZEH住宅に欠かすことができない断熱性が高いレベルで備わっているので、一般的な住宅と比べてわずかな太陽光発電でZEHにすることができます。そのため、屋根の形状も他の商品そのままに、こだわりの外観を実現。
長く住むマイホームだからこそ、未来スタンダートな仕様で高性能な住まいづくりがおすすめです。
hus Premie Gården(ヒュースプレミエゴーデン)の坪単価は80万円~100万円程度

ヒュースプレミエゴーデンの坪単価は80万円~100万円程度となっています。
ヒュースプレミエゴーデンは、スウェーデンハウスが誇るトップレベルの住宅性能に支えられた豊かな日々を、さらに上質へと昇華させた高級邸宅です。その高い性能を活かしたコンバーチブルガーデンという、庭を屋内にまで取り込んだ空間は人と自然を限りなく近づけます。
スウェーデンハウスは自然との調和を大切にしているので、あえて過度なデザインはしません。無駄をそぎ落としたデザインは、年月とともに深みが加わる風景の中で、家族を支えてくれるでしょう。もちろん、デザイン性が低いといったようなことはなく、北欧のデザイン哲学をベースにしたインテリアデザインまで、日々の暮らしをトータルにデザインしてくれます。
スウェーデンハウスの平屋の坪単価
スウェーデンハウスの平屋の坪単価については、下記記事に詳しくまとめています。
平屋を検討している方は、参考にしてみてください。
> スウェーデンハウスの平屋の価格は?建築実例や坪単価のご紹介!
スウェーデンハウスの実際の建築事例から見る、3階建ての間取り
実際の建築事例から、3階建ての間取りと坪単価を見ていきましょう。
建築事例は、公式ホームページやSUUMOから参照している情報を引用いたします。
約21坪の敷地に夢とこだわり、快適な暮らしを叶えた3階建て住宅

| 間取り | 3LDK+小屋裏 |
| 延床面積 | 37.5坪坪(124.02m2) |
| 本体価格 | 3,000万円~3,499万円 |
| 坪単価 | 80.0万円~93.3万円 |
都市部にある間口5.6m、約21坪の細長い土地を有効活用した3階建て住宅です。1階にはほぼ半分を占めるビルトインガレージを配置し、残りのスペースには書斎と大容量が収納できる納戸を設けています。
2階にはLDKとコンパクトな水まわりを配置。LDKは自然と家族が集まるよう広い間取りにし、キッチンに吊り戸棚を設けないなどの工夫でさらに広々とした空間をつくりだしています。また、バルコニーへつづく窓は観音開きの掃き出し窓を採用し、リビングと一体のように使える設計となっています。
3階は主寝室と子ども部屋を配置。主寝室には大型のウォークインクローゼットを設け、すっきり片付けられるよう考慮しています。
子ども部屋はロフトベットを設け、その下に勉強机を置くなど空間の有効活用に力を入れています。将来2部屋に仕切れるようドアや窓、収納も2つ配置しています。
スウェーデンハウスのメーカーの特徴
孫世代まで受け継ぐことのできる品質
スウェーデンには「親の代で家を建て、子の代でサマーハウス(別荘)を、さらに孫の代ではヨットを。」いう言葉があるほど、家を住み継いでいく良質な資産として扱っています。スウェーデンハウスもこれをもとに、「世代を超えて住み継げる家を届けたい」という理念から高性能なワンスペックの家をつくり続けているのです。
100年家族を守り続ける強い家を創業当時からコンセプトに作り続けているので、基本構造は不変となっています。そのため、将来的に傷みや不具合が起きたとしても、その部分を補修するだけで長く住み続けることができるのです。世代を超えて住み継いでいけると考えると、少々値は張りますがそれだけの価値がある住まいといえるでしょう。
50年間無料定期健診システム
人が暮らす住宅にも寿命があり、日本の家は平均的な寿命が30年前後といわれています。より長く住み続けるためには定期的な点検やメンテナンスが欠かせませんが、多くのハウスメーカーは長くても30年程度が保証期間となっています。一方スウェーデンハウスが行っているのが50年間の無料定期検診システム。
長く住み続けることができる家を建てるだけでなく、その後半世紀にわたって見守り続けてくれます。どんなに丈夫な家でも、何かしらの原因によって不具合が生じる可能性は0にはできません。そして、その不具合に気づくことなく放置し続けると後に莫大な修繕費を必要とするリスクも生まれます。不具合の早期発見のためにも、定期的なアフターサービスは魅力的ですね。
北欧スタイルのデザイン
スウェーデンハウスの大きな特徴はやはり北欧デザインでしょう。
スウェーデンの住宅を日本人が住みやすいようにアレンジしているので、日本にいながらまるで海外のような特別な空間を楽しむことができます。北欧のデザインが好きな方は、検討してみる価値があります。自然と人が近い距離で暮らすという点にもこだわっているので、ガーデンやインテリアにも多くの工夫があります。
マイホームを本当に心地よい空間にするために、ゆったりとした時間の流れるスウェーデンハウスの住宅はおすすめです。
スウェーデンハウスの家の性能
スウェーデンハウスの家の性能についてはどうでしょうか。
耐震性について
スウェーデンハウスの住宅は、日本の地震にも対応できるのかと疑問に感じる人もいるかもしれませんが問題はありません。2003年に行われた大規模な振動実験では、阪神・淡路大震災の2倍にあたる1,636ガルの振動をはじめとした計19回の震度6以上の揺れの後でも、補修を必要としない状態で生活空間が守られています。
これを実現しているのがモノボックス構造とよばれる、従来の軸組構造とは違い床・壁・天井の6面で地震の揺れを受け止め、分散させる構造です。従来の軸組構造では各々の接合ぶに衝撃が集中してしまい、ダメージを受けやすくなっていましたが、モノボックス構造にはその心配がありません。
断熱性について
スウェーデンハウスは日本の住宅メーカーの中でもいち早く「全棟高性能保証表示システム」という断熱性・気密性を表すシステムを導入しており、その断熱性能は日本のハウスメーカーの中でもトップクラスです。元々スウェーデンは北欧の寒い地域にあり、スウェーデンハウス自体も北海道からスタートしたことから断熱性には並々ならないこだわりと自信があります。
家全体を分厚い断熱材で隙間なく囲みこむことによって外気をシャットアウト。まるで魔法瓶のような高性能な断熱構造となっています。また、外気からの影響を強く受けやすい窓には「3層ガラス」を採用。ガラスの中空層にアルゴンガスを注入することでより高い断熱性を実現しています。さらに窓枠はアルミサッシなどの金属が一般的ですが、アルミサッシに比べて約1,700倍の断熱性能を誇る木枠のサッシによってダブルの断熱性能となっています。
耐火性について
スウェーデンの耐火性能は省令準耐火構造が標準仕様となっており、一般的な木造住宅と比較して防火性能は優れています。火に強い木と不燃材料を使うことによって優れた耐火性を発揮。火災が起きても、燃え広がりにくい工夫が施されています。省令準耐火構造の住宅は保険会社が信頼する条件となっており、火災保険が半額以下にまで抑えることができるのも魅力的でしょう。
スウェーデンハウスを選ぶメリット
長く快適に暮らすことができる
スウェーデンハウスのメリットは北欧デザインのオシャレさと「100年住み継ぐことができる」という高い性能を兼ね備えていることでしょう。
北欧デザインの外観は日本では珍しく、こだわりの外観は人の目を惹きつけます。外観だけでなくインテリアもトータルサポートしてくれるので、非日常感のあるゆったりとしたオシャレな空間に仕上がります。時代によって流行りは移り変わっていくものですが、北欧スタイルは廃れづらく未来まで飽きないマイホームとなるでしょう。
また、スウェーデンハウスの住宅を語る上で、その高い性能は外せません。前述のとおり、他のハウスメーカーに先駆けて「全棟高性能保証表示システム」を導入したスウェーデンハウスはその高い気密性・断熱性には定評があり、日本でもトップクラスの性能です。もちろん断熱性以外の性能も高く、その1つに耐久性があります。スウェーデンでは家は次の代へ引き継いでいく資産なので、日本の住宅と比較すると多くの劣化しない工夫が施されています。その秘密は通気工法にあり、構造躯体を乾燥状態に保ち続けることによって、木が劣化しないように工夫されています。
スウェーデンハウスのデメリット
坪単価が高い
スウェーデンハウスの最大のデメリットは、何といってもその坪単価の高さにあります。
坪単価が80万円~100万円というのは一般的な工務店してはるかに高く、誰でも手が届くような金額ではありません。最も安い商品でも、大手のハウスメーカーの中でグレードの高い商品程度の価格設定となっているのは少々敷居が高いと感じてしまうでしょう。
間取りに制約が多い
スウェーデンハウスは、創業以来変わらない基本構造を採用していることもあり、間取りに多くの制約があります。ハウスメーカーの商品に間取りの制約ができるのはスウェーデンハウスに限った話ではありませんが、価格帯が高いからこそ、もう少しこだわってみたいという人もいるでしょう。使用している木質パネル鵜の関係もあり60㎝単位での調整しか行うことができないので、完全自由設計で間取りにもこだわりたい方には向いていないかもしれません。
会社情報
スウェーデンハウスは名前からも連想できるように、スウェーデンの輸入住宅を取り扱っているハウスメーカーです。スウェーデンは北欧の寒い地域なので断熱性の技術をいち早く取り入れており、高気密・高断熱が重要視されています。スウェーデンで生産が行われているので北欧テイストの住宅となっており、北欧デザインが好きな方から高い人気があります。輸入住宅のため少々価格は高めとなっていますが、北欧の住宅が気になる方はぜひ検討してみてください。
| 会社名 | スウェーデンハウス株式会社 |
| ブランド名 | スウェーデンハウス |
| 本社住所 | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー23F |
| 創業 | 1964年 |
| 資本金 | 4億円 |
| 従業員数 | 850名人 |
| HP | https://www.swedenhouse.co.jp/ |
スウェーデンハウスの対応エリア
北海道
東北地方(宮城県)
関東地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県)
中部地方(新潟県、石川県、富山県、福井県、長野県、静岡県、愛知県)
近畿地方(兵庫県、滋賀県、大阪府)
中国地方(広島県)
九州地方(福岡県、大分県、長崎県)
スウェーデンハウスの2024年4月のキャンペーン・イベント一覧
スウェーデンハウスの2024年4月のキャンペーン・イベント情報の一部を紹介します。
詳細情報は、スウェーデンハウスの公式ホームページをご確認ください。
キャンペーン

<イベント内容>
期間中にスウェーデンハウスで注文住宅を建てると、以下の素敵なアイテムいずれかをプレゼント!
特典1:ルイスポールセンの照明セット
特典2:レ・クリントの照明セット
| 2024/4/1~6/30 | スウェーデンハウスの全国のモデルハウス |
実際にスウェーデンハウスで家を建てた方の満足度評価と評判・口コミ
スウェーデンハウスで家を建てた方の満足度評価
実際にスウェーデンハウスで家を建てた方29人に各項目の満足度を調査しました。

| 機能性満足度 | 8.79点/10.0点 |
| 外観デザイン満足度 | 8.52点/10.0点 |
| 内観デザイン満足度 | 8.52点/10.0点 |
| 保証・アフターサービス満足度 | 7.79点/10.0点 |
| スタッフの対応満足度 | 7.52点/10.0点 |
| 料金満足度 | 6.69点/10.0点 |
| 総合満足度 | 7.97点/10.0点 |
スウェーデンハウスの評判・口コミ
スウェーデンハウスの評判・口コミを以下の参考サイトで集めてみました。
口コミ参考サイト:https://minhyo.jp/
良い評判・口コミ
住宅性能は、他社より優れています。
評価: 5.0
注文住宅の購入にあたり、住宅展示場を複数件巡りまして、最終的にスウェーデンハウスを選択しました。選択した理由は、住宅機能が優れていることでした。居住地が北海道なので断熱性能を重視して選択しましたが、断熱効率は、日本のハウスメーカーでは一条工務店くらいしかスウェーデンハウスと同等レベルのメーカーは無いのではないかと思います。冬の住宅展示場も視察しましたが、窓の気密性が非常に高く、とても暖かかったです。また、デザインも、洋風を基調にしたデザインで非常に気に入りました。ただ、坪単価が非常に高いので、コスト面を心配される方はお勧めしません。個人適には大満足です。
スウェーデンハウスの断熱性能は日本のハウスメーカーの中でもトップクラスです。魔法瓶のような高性能な断熱構造となっており、外気からの影響を受けやすい窓には3層ガラスを採用しているため高い断熱性を実現しています。
お値段なりに素晴らしい!北国最適住宅
評価: 4.0
スウェーデンハウスを選んだのは、北海道に一戸建て住宅を建てるからです。高断熱高気密住宅は、他のハウスメーカーも出しているのですが、「薪ストーブを入れるのならばスウェーデンハウス」というイメージがあり、安心のスウェーデンハウスを選びました。それに見た目の外国住宅感は、やはりその他のハウスメーカーには出せない味だと思いました。確かにやや高めの建設費用なのですが、保証及び対応もしっかりしていて私はとても気に入っています。
スウェーデンハウスの特徴である北欧デザインは大きい魅力ポイントです。海外に住んでいるような環境で生活することができそうですね。
かわいいデザインと確かな性能
評価: 4.0
北欧風のデザインが好きなのでスウェーデンハウスを利用しました。最初はあまり聞いたことのないメーカーなので不安でしたが、実はとても高性能でした。スウェーデン自体とても寒い地域で住宅の技術がとても進んでいます。そのため、壁に使われている木材やガラスが分厚いです。よって夏は涼しく冬は暖かいです。また、家全体に換気扇が付いているので、汚れた空気が溜らないので清潔です。デザインも北欧らしい自然を感じられる可愛い見た目です。
デザインにも満足でき、性能にも満足ができるのは嬉しいですよね。スウェーデンハウスは断熱性だけでは無く耐震性や耐火性にもこだわりのあるメーカーです。
悪い評価・口コミ
良い口コミは上記で紹介したもの以外にもたくさんありますが、一方でネガティブな評判・口コミも多数存在しています。
マイホームは人生最大級の大きな買い物なので、ハウスメーカー選びは非常に重要です。ポジティブな意見だけでなく、ネガティブな意見もしっかり見た上で検討すると良いでしょう。
通りがかりのものです。唐突にすみません。
住んでいる地域と、間取りにもよると思いますが夏は猛烈暑いデス!!私の家は群馬県で、風通しのよい家なら夏もエアコン知らず、という家さえあるような地域です。もちろん最近は少ないと思いますが。
夏はエアコンなしでは死にます。
うちは1階のLDKに1台と和室に一台。2階は3部屋中の2部屋に設置してあります。そのため設置してない部屋のために2部屋のドアを開け放ち涼しくなるようにしています(-。-;
とにかく夏はエアコンはほぼ一日中全室つけています。なぜなら一度部屋が温まるとなかなか冷めないからです。だからエアコンをつけ始めたら夏が終わるまでほぼフル稼働って感じ。おかげで家にいる限りは暑さ知らずですが。
そんなにつけていたら電気代が高くなると思いましたが、せいぜいトータル10000から15000円程度。冬より断然安いです。
とはいえエアコン生活は快適とは言えません。外の暑さとのギャップのせいなのか、ほんとなら夜くらい風を通して眠りたい日もあります。
しかしこのスウェーデンハウス、掃き出しのドアが少ないから、そして窓の開き方がアレだから、兎にも角にも風通しが悪い!!!
そよ風が気持ちのよい日さえ、うちはなぜか暑い!!
長くなりましたが、エアコンの設置は必須(住む地域による)。用意しておければよいと思います。
それと風通しのよい作りを極力心がけることをお勧めします。
素人考えですが、南北にそれぞれ直線で結べる位置に大きめの窓が必要と思います。
南の窓がどんなに大きくても北の窓が小さいと風通しはあんまり良くないきがします。
いずれにしても専門家の意見を聞いて風通しのよい間取りにすることをお勧めします。
あと、一年中めっちゃ乾燥します。洗濯物は室内でもよく乾く。乾きにくいのは梅雨の時期くらい。他は常に乾燥が厳しい。肌には厳しい。
よい家が建ちますように。
お金はずっとかかりますので覚悟して(-。-;
戸建て検討中
ここの住宅って山とか田園風景のある田舎なんかのロケーションにはマッチするけど、都心の住宅地の中で建ってるとあまりにも周りと調和しないので難しいです。一応候補として話をしてみると子供からシルバニアファミリーみたいな家で恥ずかしいし、人呼びたくないと言われ即却下だった。嫁は近代的なモダンデザインの住宅がお好みなので、あなた頭おかしいと言われる始末。
好きなんだけどなぁ。。
名無し
設計さんはしっかりしていたけど、インテリアコーディネーターが本当に外れだった
こちらの要望を伝えても「んー…」のみで、かといってアドバイスらしいアドバイスはない
結局ほとんど自分で決めた
これでコーディネーター分の料金取られてると思うと納得いかない
評判・口コミの総評
スウェーデンハウスの評判・口コミを見てみると、家の性能の高さと北欧デザインに満足しているコメントが多く目立ちました。一方で低い評価の口コミを見てみると、家を建てる地域との相性などについてのコメントが多いように感じました。
スウェーデンハウスの特徴でもある北欧デザインの好みは一緒に住む家族の中でも分かれることもあるでしょう。また、家を建てる地域と雰囲気がマッチするか、という問題が気になる方も居るかもしれません。
とはいえ、感想は人によって大きく異なるので、良い口コミだけを信じてスウェーデンハウスに決めたり、悪い口コミをそのまま真に受けて検討を辞めてしまうのはあまり望ましくありません。
大切なのは、複数のハウスメーカーをしっかりと比較した上で、実際に自分自身で話を聞いてみて、自分の理想を叶えてくれそうな注文住宅会社に依頼するべきです。
スウェーデンハウスの坪単価についてのよくある質問
-
スウェーデンハウスの平均坪単価はいくら?
-
スウェーデンハウスの坪単価80万~100万円程度です。
-
スウェーデンハウスの坪単価を安くする方法はある?
-
スウェーデンハウスの営業さんに金額交渉してみると良いでしょう。金額交渉する際はライフルホームズやタウンライフなどの一括資料請求サービスで他ハウスメーカーの見積もりを貰って、その金額をベースに交渉すると良いでしょう。
ただし、無理な金額交渉は営業さんの熱を下げてしまい、結果良い家にならない可能性もあるので注意しましょう。
-
スウェーデンハウスで30坪の家を建てる際に総額いくらかかる?
-
スウェーデンハウスで30坪の家を建てる場合は、本体価格2,400万円~3,000万円程度です。この価格に、付帯工事費や諸経費などで2割~3割程度プラスした 3,200万円~4,000万円程度が実際にかかる建築総額です。
-
スウェーデンハウスの特徴は?
-
スウェーデンハウスの特徴は以下です。
・孫世代まで受け継ぐことのできる品質
・50年間無料定期健診システム
・北欧スタイルのデザイン
・「全棟高性能保証表示システム」という断熱性・気密性を表すシステムを導入
・坪単価は高め
-
スウェーデンハウスの悪い評判はある?
-
スウェーデンハウスはネガティブな口コミもありますが、ポジティブな口コミも多いです。
詳しくはこちらを参考にしてください。
ハウスメーカー選びを失敗しないためのポイント

まずは複数業者の見積もりを取ろう
注文住宅を建てる際に依頼するハウスメーカーや工務店は全国で1000社以上存在します。その中には、いわゆる欠陥住宅を建ててしまう会社も存在します。
多くの人にとって注文住宅は人生で1度きりの大きな買い物。『何千万円をかけて建てた夢のマイホームが欠陥住宅でした』では人生の取返しがつかなくなってしまうかもしれません。
そんなハウスメーカー選びで失敗しないために絶対におこなうべきことは、複数の業者を比較検討することです。
業者ごとに、費用、施工方法、建材、可能なデザインなど全く異なります。ホームページなどの情報を見て、一発で自分の希望に沿えるハウスメーカーを見つけることはとても難しいです。まずは複数の業者から見積もりや間取り設計を貰うことで、自分の理想を実現できそうなハウスメーカーをピックアップすることができます。
ただし一社ずつ自分で見積もり相談をすると、大変な労力と時間を使うことになってしまいます。複数の業者比較は、タウンライフやライフルホームズなどの一括資料請求サイト使うと簡単に比較することができるので、それらを利用すべきです。
どの一括資料請求サイトを利用すべき?
一括資料請求サイトは複数あり、どのサイトも一長一短があるので、どのサイトを利用すれば良いのかも迷ってしまうでしょう。
それぞれのサイトについて、一覧形式でまとめてみました。
結論から言えば、注文住宅初心者の場合は「タウンライフ」か「LIFULL HOME’S」がおすすめです。LIFULL HOME’Sかタウンライフを利用しておけば「ハズレ業者」を引くリスクは軽減されるでしょう。
注文住宅の検討し始めで、理想のマイホームのイメージを固めるために一括でカタログを取り寄せたい方は「LIFULL HOME’S」を
すでに検討が進んでおり、「家の間取り」などを細かく決めていきたいという方は「タウンライフ」を選ぶと良いです。
情報が多いに越したことはないので、両方ともやっておくことをオススメします。
タウンライフがおすすめな理由
タウンライフがおすすめな理由を紹介します。
タウンライフとは?
まずタウンライフとはどのようなサービスなのか説明します。
無料であなた専用の家づくり計画書を作ってくれる
たった3分でネット一括依頼ができる
厳選された優良注文住宅会社600社から相見積もりを取れる
タウンライフは注文住宅会社を比較するためのツールだと思ってください。希望のエリアを入れて計画書作成依頼することで、複数の会社があなたの希望に合わせた「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」を作成してくれます。この間取りプランや見積もりなどを比較した上で、あなたの希望に合いそうな注文住宅会社と話を進めることができます。
ある程度依頼するハウスメーカーを決めている方でも、他社の見積もりと比較して、料金交渉などもおこないやすくなるので、基本的にはどなたでもまずは一括資料請求サイトを利用した方が良いでしょう。
タウンライフのおすすめポイント
注文住宅会社比較サイトはいくつかありますが、その中でもタウンライフを使った方が良い理由を説明します。
① 注文住宅部門で3冠達成!

タウンライフは第三者機関の調査で、「利用満足度」「知人に勧めたいサイト」「使いやすさ」の部門において3冠を達成しています。
使いやすさと、一括請求で得られる資料の内容をトータル的に考えると、タウンライフが一番人気なのも納得です。
② 厳格な基準をクリアした600社の優良注文住宅会社を掲載
例えば、他の一括資料請求サービスだと複数の注文住宅会社を掲載しており、その中から自分で選んでカタログや見積もりを貰うことができるシステムですが、この注文住宅会社の中には、あまり良くないハウスメーカーや工務店が混ざっていることもあります。タウンライフの場合は、独自の厳格な基準にクリアした優良注文住宅会社しか掲載できないため、良くない会社を引いてしまう可能性が低いです。
まずはタウンライフを利用して、良い業者が見つからなかった場合は他の一括資料請求サイトを利用するという使い方が一番安全でしょう。
③ カタログでは得られないあなたの好みに合わせた間取り提案書を作成してくれる
注文住宅の資料請求サイトだと、カタログしかもらえないケースが多いです。カタログだけ見てもなかなか理想のマイホームを想像するのは難しいですし、実際に建てようと思った時に、オプション費用などで想定より高額なってしまい、結局一から考え直さなければいけなくなってしまうケースもあり得るでしょう。
タウンライフはしっかりとあなたの希望に合わせた間取り提案書と見積書を用意してくれるので、より具体的に想像することができるでしょう。なお、あなたの希望にそったオリジナル間取りプランまで用意してくれるサイトは日本でライフタウンのみとなっています。
④ 土地探しをおこなってくれる
土地探しは注文住宅を建てる上で、人によっては一番めんどうに感じるかもしれません。とくに業者に頼まず自分で土地を探す場合は、購入した区域によっては建築規制があり、自分の思い描いていた家を建てられなくなってしまったというケースもあり得るでしょう。
また、一つのハウスメーカーに土地探しを依頼したけど、あまり良い土地が無いというケースもあります。土地の取り扱いはハウスメーカーによって異なるので、土地探しで失敗しないコツは複数業者から土地提案を貰い、理想の間取りと自分が実際に生活することをイメージして、最適な場所を選ぶ必要があります。
タウンライフなら、間取り設計と見積もりだけではなく、専門家ならではの土地提案までもらえるので、「より失敗しない家づくり」をおこなえるでしょう。
他にも、毎月先着で99名様に「成功する家づくり7つの法則」という49ページの小冊子をプレゼントしているなど、メリットが多いです。注文住宅の資料請求サイトの中なら個人的にはタウンライフ一択ですね。
LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)がおすすめな理由
LIFULL HOME’Sがおすすめな理由を紹介します。
LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)とは?
まずLIFULL HOME’Sとはどのようなサービスなのか説明します。
一部上場企業「株式会社LIFULL」が運営している安心感
たった数分で、複数のハウスメーカーの一括カタログ請求依頼ができる(無料)
掲載のハウスメーカーはLIFULLが厳選した優良住宅メーカー
LIFULL HOME’Sは注文住宅のカタログを一括で無料お取り寄せできる、資料一括請求サービスです。
注文住宅の検討を始めたばかりの方はこちらのカタログ一括請求サービスを利用すると良いです。
注文住宅の最初の一歩目は「どんな家を建てたいか、イメージを具体化すること」です。
LIFULL HOME’Sなら、あなたが検討している地域に対応しているハウスメーカーのカタログを一括請求できるので、そのカタログを見て、どんな家を建てたいかイメージを固めましょう。
LIFULL HOME’Sのおすすめポイント
注文住宅会社比較サイトはいくつかありますが、その中でもLIFULL HOME’Sを使った方が良い理由を説明します。
① 全国のハウスメーカーのカタログ資料を無料で簡単に手に入れられる
LIFULL HOME’Sでは、あなたのご希望の地域を選択し、気になるハウスメーカーをチェックして、必要情報を入力するだけで、簡単に複数のハウスメーカーのカタログを取り寄せできてしまいます。
もちろん、全て無料で利用可能です。
もしLIFULL HOME’Sのようなカタログ一括請求サービスを利用しない場合は、1社1社全て自分で電話などをおこない、都度自分の情報を伝えて、ヒアリング&営業トークを聞き、とても疲弊してしまうことでしょう。
1社1社連絡を取るのが面倒になり、最終的に「もうこの会社でいいや」と、妥協してしまうかもしれません。
そんなことにならないように、楽できるところはしっかり楽しましょう。
② 日本最大級の不動産サイトを運営している「株式会社LIFULL」が運営
LIFULL HOME’Sは東証一部の大手不動産サイトを運営している「株式会社LIFULL」がおこなっているサービスです。
一括資料請求サイトは自分の情報を入力する必要がありますが、大手の「株式会社LIFULL」が情報を管理してくれるなら安心ですね。
③ 今なら「家づくりノート」がもらえる!!
LIFULL HOME’Sでカタログ請求をすると、今なら「家づくりノート」がもらえます。
これはLIFULL HOME’Sが、家づくりのためのお金や土地・スケジュール・見学会など、知っておきたいことを一冊にまとめてくれた、注文住宅検討者にはとても有難い小冊子です!
夢のマイホームで失敗しないためにも、ぜひ下記から資料請求してGETしてみてください!
坪単価についての基本情報

当ページでは、主に各メーカーの坪単価について紹介していますが、そもそも坪単価について詳しく知らないという方もいるでしょう。ここでは、坪単価のことを詳しく紹介していきます。
坪単価とは
家を建てる際に「坪単価」という言葉をよく目にすると思います。この坪単価とはいったい何のことなのでしょうか。
坪単価とは、建物の本体価格から建てた家の総床面積で割って出した金額のことを言います。
例えば、40坪の家を2,000万円で建てた場合2,000万円×40坪=50万円/坪と計算し、坪単価は50万円となります。
坪単価の平均相場について
国土交通省の令和2年の統計データを参考にすると、全国の平均坪単価は約70万円となります。
しかし坪単価は土地や家の構造、依頼するハウスメーカーによって変わってくるので一概に平均で見るべきではありません。
例えば、東京の平均坪単価は81万5,800円程度ですが、一方北海道の平均坪単価は約60万円となっています。
また構造別の平均坪単価は以下のようになっています。
| 家の構造 | 平均坪単価 |
| 木造 | 56万8,000円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 92万3,000円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 91万5,000円 |
| 鉄骨造 | 76万1,000円 |
一般的に木造に比べて鉄筋コンクリートを使用した家のほうが、坪単価は高くなります。また当然ですが、物価が高い地域ほど坪単価は高くなります。
同じハウスメーカーで同じグレードの家を建てることを考えても、坪単価は大きく変わってくる場合もあります。50坪の広さと30坪の広さに同じメーカーの同じグレードの家を建てるとしても総額はもちろんのことですが、坪単価も変化することがほとんどです。
キッチンやバスルーム、トイレなどの設備は高額で、広い家でも狭い家でもどちらも同じ数を設置する必要があります。これらのような設備は高額であるため、建築費用の総額では広い家の方が料金は高くなりますが、坪単価で見ると狭い家の方が高くなります。
坪単価だけでは検討できない部分が多いため、自分が住みたい地域で一括見積りなどをおこない、建築費用の相場を確認すると良いでしょう。注文住宅会社の一括見積もりサイトを見たい方は下記のページにまとめているので、あなたにあった見積もりサイトを選んでください。
坪単価を見る際の注意点
坪単価は家の本体価格から家の面積を割った1坪あたりの費用と表現されますが、この家の面積については定義があいまいとなっています。
例えばベランダや車庫、地下室などは建築基準法で延床面積に含まれませんが、計算の際にはこの部分の面積を入れて計算する業者と、入れずに計算する業者が存在します。
全く同じ家を建てたとしても坪単価として計算する面積の定義によっては、坪単価は大きく異なることになります。
ベランダなども全て含めた面積は「施工面積」と呼ばれ、通常はこの総合施工床面積で坪単価を計算することが多いです。ハウスメーカーに依頼する際は、「施工面積」と「延床面積」どちらで坪単価計算されているか確認しておくと良いでしょう。
また、本体価格の他にも付帯工事や諸経費などが発生してくるので、トータル金額を確認すると良いでしょう。
坪単価以外に考えなければならない費用
実際に注文住宅を建てる際は、本体価格の他にどんな費用が発生してくるのか、細かく確認します。
金額としては、全て合わせると本体価格の2~3割増しで考えると良いです。
付帯工事費(全体費用の1割~2割程度)
①基礎補強工事関連費用
地盤が弱い場合に、地盤を補強する工事です。地盤調査を行い、固い地盤まで深堀して杭をうつ作業や、セメントなどで地表面を固める作業をおこないます。
②インテリア関連費用
インテリアを揃える費用です。家具は前の家から持ってくることもできますが、例えばカーテンは新しい家の窓に合わせて新調する必要があります。また新居に合うような家具に買い替えるケースも多いです。その他、エアコンや照明器具の費用なども含まれます。
③エクステリア関連費用
庭や外の塀、玄関の門、ガレージなどを作るための費用です。
諸経費(全体費用の1割程度)
①登録免許税
家を建てるにあたり、法務局に登記の申請をおこなう必要があります。この登記をおこなう際にかかる税金のことです。固定資産税評価額の0.1%程度と考えておくと良いでしょう。
②不動産取得税
不動産を取得したときに発生する税金です。固定資産税評価額を基に計算されます。
③火災・地震保険費用
火災と地震の際の保険です。ほとんどの方が加入しています。
その他地鎮祭や上棟式をおこなう場合は「式祭典費用」、各種契約書の「印紙代」、住宅ローンの手続き費用などが発生します。
坪単価を安く抑える方法
坪単価を安く抑える方法をいくつか紹介します。
門扉やフェンスを作らない
エクステリア費用として占める割合が多いのが門扉とフェンスです。家を建てる際、最初はほとんどの人が作りたいと思うでしょうが、実際に住んでみると、設置の必要はないと感じる方も少なくないでしょう。
1階と2階の面積を同じにする
1階と2階の面積を同じにすることで、基礎や柱などが最小限で済むため、コストを抑えることができます。
屋根をシンプルにする
せっかくの注文住宅なので、家の外観にはしっかりこだわりたいですよね。ただ、坪単価を抑えるためには、我慢をしなければいけない部分がでてきます。
屋根の形には「片流れ」「切妻」「寄棟」などがありますが、シンプルなデザインにすることでコストカットをおこなえます。
外壁の形をシンプルにする
外壁もシンプルな四角より、凹凸があった方がカッコよく感じるかもしれませんが、凹凸を作ると外壁量が多くなってしまいます。
外壁も屋根と同様にシンプルなデザインにすることでコストカットに繋がります。
他にも建築費用を抑える細かいテクニックはあるので、必要に応じて調べてみると良いでしょう。ただし、建築費用を左右するのは細かいテクニックより、依頼する注文住宅会社選びでしょう。こだわりを我慢して費用を節約した結果、理想の家とは程遠くなってしまっては意味がありません。
まずは、あなたの理想の家を、理想の価格で建てることができる会社選びをしっかりおこなうことが最重要と言えます。
注文住宅会社選びは一般的に一括見積りサイトを利用して、厳選していくことになりますが、どこの一括見積りサイトを使えば良いかがわからない方も多いでしょう。
以下のページで一括見積りサイトの比較をおこなっています。あなたの検討状況に合わせて、使用する一括見積りサイトを決めてください。
スウェーデンハウスのアンケート調査概要
調査日:2022年10月24日~2022年10月31日
集計対象:事前調査で「大手ハウスメーカーで注文住宅を建てたことがある」と回答した20歳以上の男女
調査人数:事前調査12016人/本調査29人
調査機関:サーベロイド(株式会社マーケティングアプリケーションズ)
調査依頼:おうちパレット
●アンケートについて
インターネット調査機関のサーベロイドを利用して、実際に注文住宅を建てたことのある12016人のうち、「スウェーデンハウスに依頼した」と回答した29人に対して、建てた家のアンケートを実施しました。
スウェーデンハウスで建てた方の住宅データ
質問1:建てた家の坪数を教えてください。

スウェーデンハウスで建てた方の平均坪数は44.4坪でした。
質問2:建築価格を教えてください。※土地代含まず

スウェーデンハウスで建てた方の平均建築価格は3572万円でした。
スウェーデンハウスの満足度アンケート結果
質問3:スウェーデンハウスの機能性満足度(断熱性・耐震性・遮音性など)を10点満点で評価してください。

スウェーデンハウスの機能性満足度の平均は10点満点中「8.79点」でした。
質問4:スウェーデンハウスの外観デザイン満足度を10点満点で評価してください。

スウェーデンハウスの外観デザイン満足度の平均は10点満点中「8.52点」でした。
質問5:スウェーデンハウスの内観デザイン満足度を10点満点で評価してください。

スウェーデンハウスの内観デザイン満足度の平均は10点満点中「8.52点」でした。
質問6:スウェーデンハウスの保証・アフターサービス満足度を10点満点で評価してください。

スウェーデンハウスの保証・アフターサービス満足度の平均は10点満点中「7.79点」でした。
質問7:スウェーデンハウスのスタッフの対応満足度を10点満点で評価してください。

スウェーデンハウスのスタッフの対応満足度の平均は10点満点中「7.52点」でした。
質問8:スウェーデンハウスの料金満足度を10点満点で評価してください。

スウェーデンハウスの料金満足度の平均は10点満点中「6.69点」でした。
スウェーデンハウスの満足度評価まとめ
| 機能性満足度 | 8.79点/10.0点 |
| 外観デザイン満足度 | 8.52点/10.0点 |
| 内観デザイン満足度 | 8.52点/10.0点 |
| 保証・アフターサービス満足度 | 7.79点/10.0点 |
| スタッフの対応満足度 | 7.52点/10.0点 |
| 料金満足度 | 6.69点/10.0点 |
| 総合満足度 | 7.97点/10.0点 |
※総合満足度は全体の平均点で算出しています。